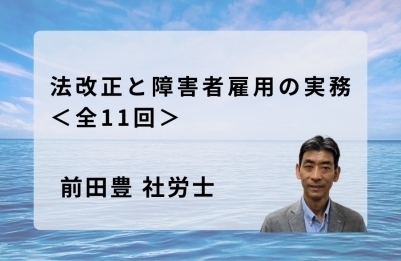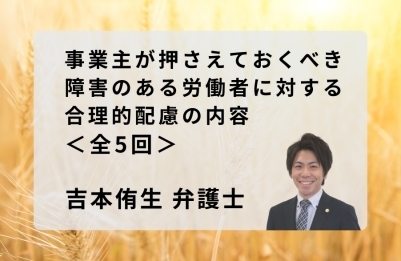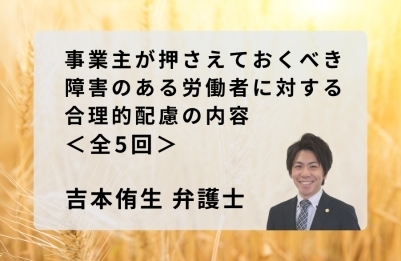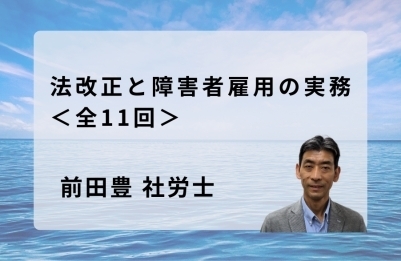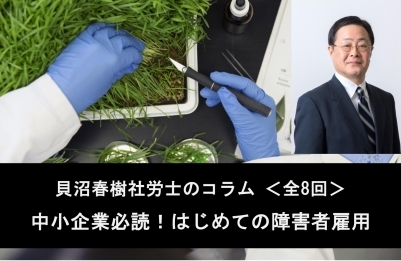<貝沼春樹社労士の連載コラム 全8回>
中小企業必読! はじめての障害者雇用
最終回 昇格・昇給条件も明示 定着促進には欠かせず
日報など活用し体調面の把握を
筆者は、社会保険労務士・精神保健福祉士として企業のメンタルヘルス対策の支援も行っている。メンタルヘルス対策と障害者雇用は共通した部分が少なくない。
メンタルヘルス対策では、上司は部下をよく観察して変化に気付き、おかしいと思ったら声を掛けて個別に話を聞き、必要な場合は産業保健スタッフ(産業医、産業看護職、保健師など)につなぐというフローが重要とされる。面談時に部下が困りごとや本音をいえる雰囲気作りも欠かせない。
障害者雇用の定着対策でも全く同じといえる。労務管理において基本となるのは、日頃から本人を観察し、丁寧にコミュニケーションをとることである。障害を持つ社員には体調の波があるのは当たり前と考える。本人の障害特性などを理解し、調子を崩しやすい状況やきっかけ、体調を崩しそうな場合のサインや兆候を把握しておく。そして、本人が発する不安や緊張、過集中(過剰に集中しすぎる状態)による疲労やストレスのサインに気付き、見逃さないようにする。気付いたら声を掛けて体調を聞き、必要に応じて休憩や面談するなどの対応を速やかに行う。
メンタルヘルス対策では対応を産業保健スタッフにつなぐが、障害者雇用では支援者に相談や支援を求めることとなる。体調不良や困りごとを社内ではいい出しにくいと感じている障害者は少なくない。終業後や休日に、医療機関のナイトケアや出身の支援機関に行き、相談している場合もある。支援者の方が話しやすいからで、就職後も企業と支援機関との連携が重要であることが分かる。定期的または随時、支援者に会社を訪問して本人と面談してもらうと、困りごとや悩みを早期に把握できるのでお勧めしたい。
社内外に提携している産保スタッフがいれば、積極的に活用・連携を図りたい。メンタルヘルス対策も業務範囲内なので、本人の不調時に主治医との連絡・調整面などで対応してもらえる。ただ、産保スタッフと連携が取れているケースは、まだ少ないようである。
不調の原因は、職場内の人間関係をはじめとした職場や仕事に関する事項だけとは限らない。家庭生活の乱れ(深夜までゲームをして睡眠不足だったなど)のほか、家族関係の悪化、休日の遊び過ぎ、勝手な通院の中断、独断での断薬――などが考えられる。このような私生活の乱れが、勤怠状況や職場内での勤務態度の悪化につながる場合がある。
企業としては社員の私生活に踏み込むのは普通、躊躇してしまう。しかし、障害者雇用の場合は、本人の家庭生活などに無関心では済まされないことがある。勤怠状況などが悪化した場合はその旨を家族に知らせ、原因が私生活にあると分かったら、家族に協力を求める。家族との連携は欠かせず、その際は障害者就業・生活支援センターや支援者に相談しながら対応すると良い。
会社が、本人の日常の業務遂行状況、困りごと、体調などを常時把握することが定着には重要となる。それらの把握に向けて、日々業務日誌を書かせたり、システム化してPCやスマートフォンで入力させているケースがある。継続して取り組めば個々人の記録が溜まり、不調になりやすい時期や仕事量、不調の兆しが分かり、事前に対策を打てる。最近は、記録付けをサポートする民間サービスも登場してきた。川崎市が展開するセルフケアを中心とした「K-STEP(川崎就労定着プログラム)」も参考になる。
障害年金受給は“就労後も”可能
障害者雇用では、1~2年の有期雇用契約でスタートし、初任時の時給は最低賃金とするケースが少なくない。法定雇用率上昇と人手不足とを見込むと、雇用条件の良い企業に求職者が集まる可能性が高く、採用環境は今後、厳しくなると思われる。
障害の有無にかかわらず求職者にとって、「その企業で将来が展望できるかどうか」は入社を決める1つの判断ポイントとなるし、処遇(昇進、ポジションなど)や賃金(昇給、給与テーブルなど)がどのようになっているか、本人の希望するライフプランに適うものかどうかも重要である。法律で定められている明示すべき事項のほか、人事評価の基準、昇進や昇格の条件、昇給ルールなどをオープンにしておけば、求職者は自分の将来計画をイメージでき、この会社に就職して長く働こうと考える。障害者雇用においても、人事処遇制度の整備に関する重要性は増している。
筆者は、障害者雇用における人事制度や評価制度の構築について依頼を受けることがある。最近は特例子会社に就職された方から、「会社からいわれたので、障害年金の申請手続きをしてほしい」との相談が寄せられた。採用時は賃金が低いので、障害年金で補おうという考えである。
就労していると障害年金は支給対象外と思い込んでいる方がいるが、決してそうではない。筆者も障害年金の申請を数多く依頼されているが、就職後であっても障害年金が認められたケースは経験している。障害年金の受給も併せて検討したい。
あおば社会保険労務士・精神保健福祉士事務所
代表 特定社会保険労務士 精神保健福祉士 貝沼 春樹
三井住友海上火災保険とその関連会社に41年勤務。営業・経営企画・人事労務、関連会社の役員等を経験。その経験を活かして経営者目線で人事労務コンサルティングを行っている。特に障害者雇用に注力。精神保健福祉士・訪問型ジョブコーチでもあり、精神障害者・発達障害者・知的障害者を雇用する企業への支援を得意としている。
https://aoba-roumu.com/