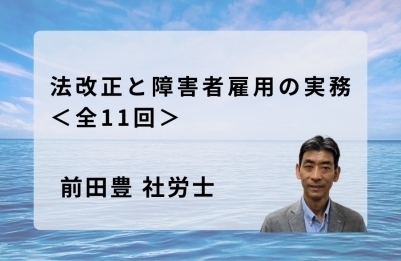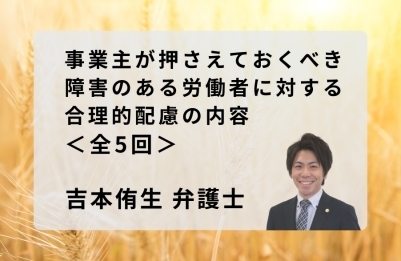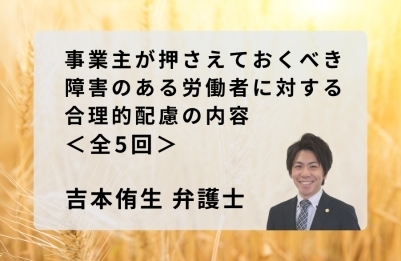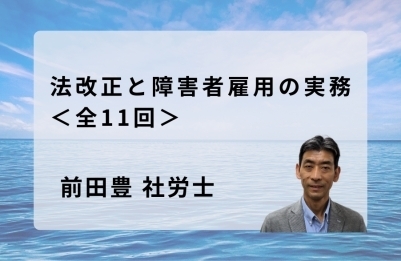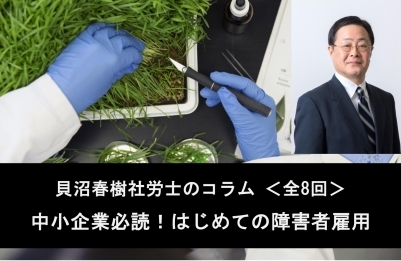<前田 豊社労士の連載コラム 全11回>
法改正と障害者雇用の実務
第4回 改正障害者総合支援法 就労選択支援制度で障害者雇用は変わるか?
就労支援におけるアセスメントの重要性
障害のあるスタッフが働きやすい職場環境をつくっていくにあたり、障害特性の理解が欠かせません。障害特性がわからなければ、何に配慮をして、職場環境を整えていけばよいかわからないはずです。
障害特性は、障害の種別により、大まかな特徴はあります。しかし、個別の特性は千差万別であります。例えば、同じ区分の知的障がいの判定を受けている2人がいたとします。Aさんはおしゃべりが大好きで、日常の会話は流ちょうにされますが、知的障がいのため大事なことの判断をするのがとても苦手です。Bさんは知的障がいのため自分から話すことはできませんが、人の言うことは理解でき、身の回りの判断もご自分でされます。
異なる特性をもった2人の職場環境をつくるにあたり、実は、福祉分野の就労支援サービスに従事する人も苦労しています。個別の特性はどこにあるのか、一概に苦手と言っても、まったくできないのか、環境を変えていけば徐々にできようになるのかなど、就労支援事業所では日々試行錯誤をしています。
福祉サービス提供のルールとして、サービス利用を開始する前に個別の障害特性を把握することになっています。これをアセスメントと呼び、障害者支援にかかわる人の職業専門性として重要な一つとなっています。
障害者就労支援サービスの分野では、アセスメント結果を活かして、個別の就労訓練プログラムを組み、日々就労訓練をしています。その後、訓練の進捗状況により、就労支援施設にとどまり続けるのでなく、一般就労へ移行したり、より障害者本人の意向を反映した働き方に移行していくことが期待されており、この期待のために就労支援事業所に多大な税金が投入されているのだと筆者は思っています。
就労の選択肢を広げる「就労選択支援制度」
実は、就労訓練の進捗により、働き方を移行させていく作業が社会全体でうまく行っていない現実があります。一度、就労支援施設を利用し始めると、ずっと施設に居続ける障害者が多いことが、国レベルでも課題になっており、過去2~3年の間に、厚生労働省の社会保障審議会の議論されました。その結果できたのが、標題の就労選択支援制度になります。
就労選択支援の制度は、主に福祉サービスの就労訓練を受けている障害者が、就労先や働き方についてより良い選択ができるよう支援します。具体的には、本人の希望、就労能力や適性等などのアセスメントをするサービスです。アセスメント結果は、ハローワーク、就労支援機関、就労先の企業とも共有し、アセスメント結果を基に、本人にあった働き方を決めていくことが、障害者雇用促進法に明記されました。アセスメントでは主に次の項目を評価することになっています。
・障害の種類及び程度
・就労に関する意向
・就労に関する経験
・就労するために必要な配慮及び支援
・就労するための適切な作業の環境
これらを客観的に評価して、本人の就労可能性を可視化するのが就労選択支援事業所の仕事になります。アセスメント結果は、就労先企業にも共有されることになっています。
障害者雇用を行う企業で、公費が入る福祉事業所と同様に、個別の障害特性の理解に試行錯誤する時間と労力を費やせるのかと言うと、難しいのではないかと思います。個別の障害特性の理解(アセスメント)の難しさは、障害者雇用が進みにくい原因の一つでもあると筆者は思っていますが、就労選択支援の制度により、アセスメント結果を企業が入手できます。これは、障害特性に配慮した、良質な障害者雇用を希望する会社にとっては、素晴らしい制度だと言えるでしょう。
就労選択支援事業は、令和7年10月より開始されることになっています。筆者は、今後の障害者雇用の推進に、大いなる希望を希望をもっています。
前田福祉社労士事務所
代表 社会保険労務士・介護福祉士 前田 豊/Maeda Yutaka
東京学芸大学卒業後、あきる野市社会福祉協議会に11年間勤務。障がい者施設で支援について学ぶ。平成23年に社会保険労務士として独立し、福祉施設の労務管理を業として行いながら、法定雇用率に関わらず障害者を雇用している中小企業の取材活動を行う。
https://usei116.com/