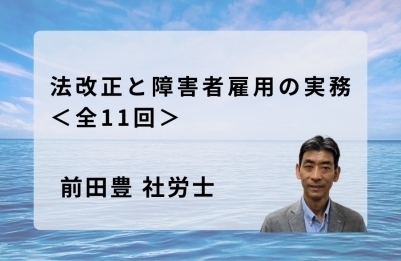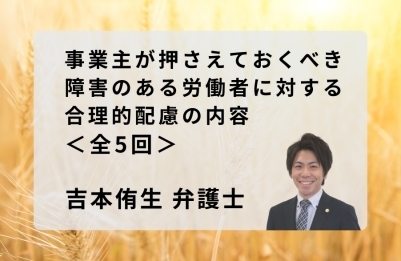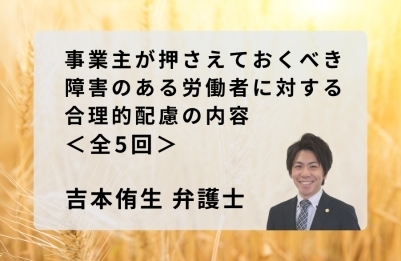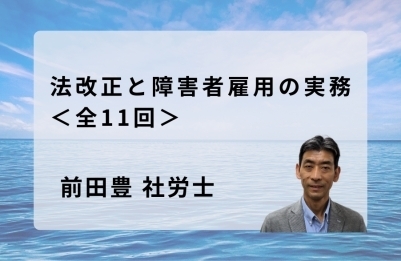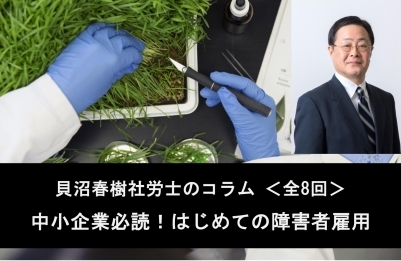吉本郁生弁護士 連載コラム
事業主が押さえておくべき障害のある労働者に対する合理的配慮の内容
第4回 障害を有する労働者に対する安全配慮義務が問題となった裁判例(前編)
1.はじめに
今回のコラムと次回のコラムでは、障害を有する労働者に対する配慮が問題となった裁判例を紹介します。
これらの裁判例は、直接的に、障害者雇用促進法(以下「促進法」といいます。)上の合理的配慮の提供義務が問題となったものではありませんが、採用後に健康上の問題が生じた労働者に対する配慮が問題となったものであり、促進法上の合理的配慮に違反した場合にも同様の問題が生じるおそれがあることから、促進法上の合理的配慮の内容を検討するに当たっても参考になるものと考えられます。
今回のコラムでは、精神的な症状が問題となった事案を取り上げます。
2.障害者に対する配慮が問題となった事例
【最高裁平成26年3月24日判決】
この事案では、液晶ディスプレイを製造する工場に勤務していた労働者(上告人)が、鬱病となって休職し、その後、会社(被上告人)から解雇されたため、鬱病は過重な業務に起因するものであって解雇は違法・無効であるとして、会社に対し、安全配慮義務違反等に基づく損害賠償などを求めました。
この事案では、労働者が通院や病名などを上司等に申告していなかったことから、高裁では、会社が労働者の鬱病の発症を回避したり発症後の増悪を防止する措置をとったりする機会を失わせる一因となったとして過失相殺を認めたため、労働者が自身のメンタルヘルスに関する情報を会社に伝えておく必要があるのかという点が問題となりました。
この事案について、最高裁は、次のように判示し、会社は、労働者からの申告がなくても、労働者の健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているとした上で、体調不良が過重な業務によって生じていることを認識し得る状況にあったことからすると、過失相殺は認められないと判断しました。
「上告人が被上告人に申告しなかった自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので、労働者にとって、自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。また、本件においては、……過重な業務が続く中で、上告人は、……体調が不良であることを被上告人に伝えて相当の日数の欠勤を繰り返し、業務の軽減の申出をするなどしていたものであるから、被上告人としては、そのような状態が過重な業務によって生じていることを認識し得る状況にあり、その状態の悪化を防ぐために上告人の業務の軽減をするなどの措置を執ることは可能であったというべきである。これらの諸事情に鑑みると、被上告人が上告人に対し上記の措置を執らずに本件鬱病が発症し増悪したことについて、上告人が被上告人に対して上記の情報を申告しなかったことを重視するのは相当でなく、これを上告人の責めに帰すべきものということはできない。……以上によれば、被上告人が安全配慮義務違反等に基づく損害賠償として上告人に対し賠償すべき額を定めるに当たっては、上告人が上記の情報を被上告人に申告しなかったことをもって、……過失相殺をすることはできないというべきである。」
このように、会社は、労働者からメンタルヘルスに関する情報の申告がなかったとしても、安全配慮義務違反が認められることがあります。
このことは、厚生労働大臣の定める『合理的配慮指針』(以下「配慮指針」といいます。)において、採用後に障害者であることを把握した場合であっても、事業主は、当該障害者に対し、遅滞なく、職場において支障となっている事情の有無を確認しなければならないとされていることと整合します。
配慮指針では、精神障害を有する労働者に対する採用後の合理的配慮の例として、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮することや、本人の状況を見ながら業務量等を調整することが挙げられていますが、これらは、まさに上記判例において求められていた対応であり、これらを会社側が行っていれば、安全配慮義務違反となることはなかったと考えられます。
このことから、促進法上求められる合理的配慮を怠り、これにより労働者の心身の健康が損なわれた場合には、安全配慮義務違反により損害賠償義務を負うおそれがあるといえますので、この点からも配慮指針に沿って合理的配慮を提供することが重要といえます。
【青森地裁令和4年9月27日判決】
この事案では、成人式の開催業務を担当していた県の職員(原告)が、業務中に意識を失って入院し、適応障害と診断されました。その後、当該職員は、職場復帰し、一旦は適応障害の治療を終えましたが、他の職員とすれ違ったことをきっかけに再度体調不良となって通院を開始し、継続的に通院治療をしていたものの、抑うつ状態となりました。
この事案について、裁判所は、原告が意識を失って入院するまでの事情と、その後の事情を分けて検討し、まず、意識を失って入院することになった点については、3か月前から時間外勤務の時間が急増して1か月あたり80時間を超えていたことや、成人式の開催業務が失敗した場合の影響が非常に大きい業務であるにもかかわらず初めてその業務を担当する原告以外に担当者がいなかったことなどから、業務上の負荷に起因して生じたものと認めた上で、原告は特に本件災害3か月前から肉体的及び精神的に相応の業務上の負荷を負っており、その程度は業務上の配慮を要する程度に至っていたとして、原告の時間外勤務の時間や業務負担を管理し、その見直しや配慮をすべき安全配慮義務を怠ったものと判断しました。
そして、入院後の事情についても、抑うつ状態と診断されるまでの約6か月間にわたり80時間程度の時間外勤務が続いており、そのような中で抑うつ状態が発症していることからすると、体調不良のきっかけが業務に直接起因するものでなかったとしても、抑うつ状態は業務上の負荷に起因して生じたものと認め、発症までの6か月間について、心身の許容する程度を超える業務上の負荷を負い、業務上の配慮を要する状態であったとして、健康を害さないよう時間外勤務の時間を管理すべき安全配慮義務を怠ったものと判断しました。
また、この事案では、原告は自身のうつ病を信じておらず、上司との面談時に原告が上司に精神面は大丈夫であると伝えていた一方、原告が上司等に残業できないことや体調不良を伝えていた事実は認められないとされましたが、上司は、原告が意識を失って入院したことを把握しており、原告から異動の要望も受けていたことから、精神疾患に関する情報については本人から積極的な申告が期待し難い性質のものであることも踏まえると、原告から精神面が大丈夫である旨を聞き、体調についての情報提供がされなかったとしても、それをもって原告に対する業務上の配慮を免れるものと解することは相当でないと判断されました。
この裁判例では、心身の状態に対する配慮ではなく、業務上の負荷の程度について配慮が必要であったと判断しており、その意味では促進法上の合理的配慮とは内容が異なりますが、この裁判例においても、上記の最高裁判決と同様、精神疾患に関する情報が本人による積極的な申告を期待し難い性質のものであることを理由に、原告本人から精神面が大丈夫であると聞いていたとしても業務上の配慮が必要であったと判断されています。
他方で、配慮指針では、採用後においては、労働者からの申出の有無にかかわらず、事業主が労働者の障害の有無を把握・確認しなければならないとされていますが、必要な注意を払っても障害者であることを把握できなかった場合には、合理的配慮の提供義務に違反したことにはならないとされており、全従業員への一斉メール送信、書類の配布、社内報等の画一的な手段により、合理的配慮の提供の申出を呼びかけている場合には、「必要な注意」を払っているものと考えられるとされています(障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A【第三版】1-5-2)。また、障害を受容していない労働者に対しては、合理的配慮の提供義務はないとされています(同Q&A1-5-1)。
この配慮指針を前提とすると、一斉メール等で合理的配慮の提供の申出を呼び掛けても、障害を有する労働者本人から申出がなかったり、労働者本人が障害を受容していなかったりした場合には、合理的配慮の提供義務はないものと考えられますが、上記の裁判例では、労働者本人が精神面について大丈夫であると言っていたにもかかわらず安全配慮義務違反が認められており、合理的配慮の提供義務がない場合でも安全配慮義務に違反することがあり得るように思われます。
この点については、上記Q&Aでは一般論を記載しているだけであり、上記の裁判例は、必ずしも上記Q&Aと矛盾するものではない(促進法上の合理的配慮の提供については判断されていないものの、合理的配慮の提供が問題になっていれば、労働者本人が大丈夫であると言っていても合理的配慮が例外的に必要となる事案であった)と考えることもできないわけではありません。
もっとも、促進法上の合理的配慮は、障害者でない労働者との均等な待遇の確保等を目的として求められるものであるのに対し、安全配慮義務は、労働者の生命・身体等の安全を確保するために求められるものであり、いずれも根拠や趣旨が異なりますし、このような内容の違いから、促進法上の合理的配慮については、労働者の意向を踏まえて当該労働者が働きやすい環境を整えるための措置を求めるものであるのに対し、安全配慮義務については、労働者の意向にかかわらず労働者の健康を確保するための措置を求めるものであると考えられ、その意味では、労働者本人が障害を受容していないなど、促進法上の合理的配慮の提供義務がない場合であっても、安全配慮義務が課されることがあるのではないかと考えられます。
この点については、裁判例などで、促進法上の合理的配慮の提供義務と安全配慮義務の関係が論じられているわけではありませんので、今後の裁判例において上記のような解釈がなされるかは分かりませんが、現時点では、事業主としては、配慮指針などで促進法上の合理的配慮の提供義務がないとされる場合であっても、安全配慮義務違反となることがあると考え、配慮措置を講じないことにより心身の健康上の問題が発生・拡大し得る場合には、本人の意向とある程度抵触し得ることがあっても、配慮措置を講じておくのが安全であるように思われます。もっとも、この場合であっても、労働者本人との話合いは重要であると考えられますので、まずは十分に話合いを行い、やむを得ず労働者本人の意向と反する措置を講ずる場合であっても、弁護士などの専門家と相談して対応を決定するのが安全です。
執筆者 弁護士 吉本 侑生/ Yoshimoto Yuki
Serenity法律事務所 代表
平成29年弁護士登録。同年、ベンチャー企業を創業からIPO・M&Aまで幅広くサポートする大阪の法律事務所に入所。同事務所にて多数の企業法務案件や一般民事事件、書籍の執筆、セミナー(個人情報等)を経験し、令和6年、大阪にて独立開業。現在は、契約書作成、労働問題、債権回収をはじめとする企業法務案件を中心に、離婚、相続、交通事故、刑事事件など幅広い案件の対応を行っている。
https://serenity-law-office.site/