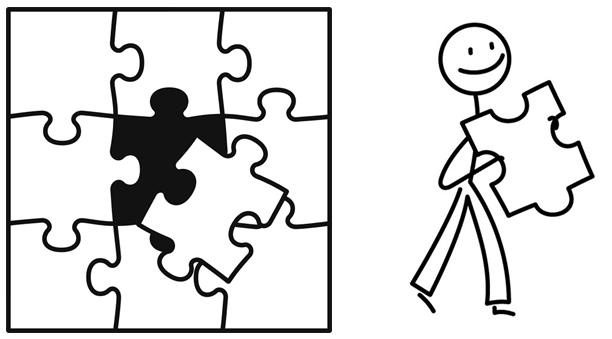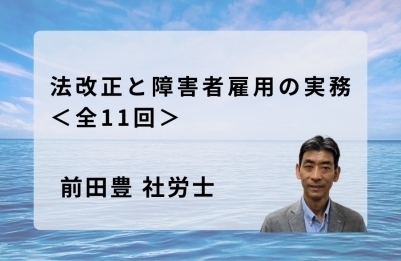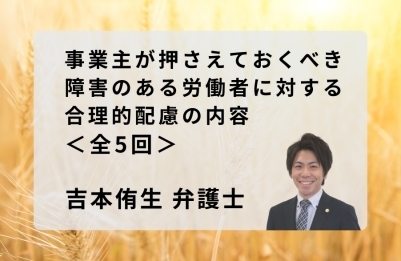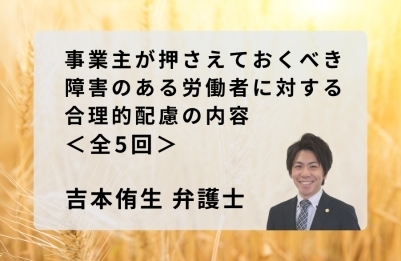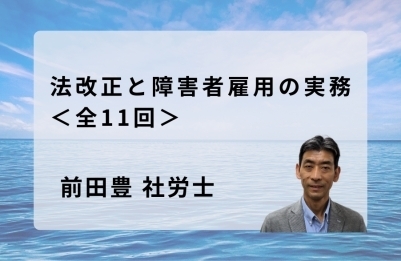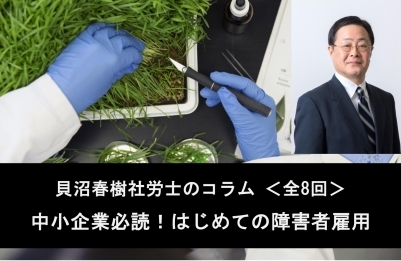前田豊社労士 連載コラム
法改正と障害者雇用の実務
第5回 障害者雇用実務 医療・福祉の現場で障害者雇用を進めていくには
医療福祉の現場において、障害者雇用を進めることは難しいとの認識が一般的ではないでしょうか。実はいくつかのポイントを押さえることで、職を求める障害者にとっても、人手不足に悩む医療福祉業者にとっても、Win-Winとなる可能性を大いに秘めています。
今回は、その意義と具体的方法について解説します。
1.はじめに厚生労働省が発表している産業別就労者をみますと、2025年推計値で、全就労人口6,491万人のうち、製造業、卸売・小売、医療福祉の3分野あわせて3,017万人であり、全就労人口の46%ほどを占めています。障害者雇用を進めていくには、就労人口の多い分野で障害者雇用の実績をつくっていくのが、障害者雇用数を増やしていくのに効果的であると考えます。
特に医療・福祉業では、今後、全就労人口が減少傾向にも関わらず従事する人の増加が見込まれている唯一
の業種であります。
医療福祉の現場において、障害のある人を雇い入れるノウハウを構築することで、障害者雇用が今後増えて
いくと考えています。
データ出典
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/01-01-03-05.html

医療福祉業界は、業態としてはサービス業に分類されます。サービス業については、障害者雇用が中々進みにくい現状があります。理由は、お客さんとのコミュニケーション、臨機応変な対応など総合的な職務能力が求められる場合が多く、障害をお持ちの方が求めている職場環境と相違のある場合が多くあるためと考えています。
筆者の会社は、障害者に就労支援のサービスを提供する福祉業になりますが、支援の現場で精神発達障害のあるスタッフを雇用しています。配慮事項としては、サービス利用者とのコミュニケーションにおいて、予め支援担当する利用者を決めて、仕事に入りやすくしています。それでも現場業務では様々なことがおきてきます。
例えば、サービス利用者から体調不良の申出がしばしばあります。申出をどの程度深刻にとらえて対応していくのかが、支援員の重要なスキルの1つです。深刻な体調不良ととらえて就労訓練を止めて休んでいただいたり帰宅を促したりするのか、または、体調不良の申出があったとしても実際には体は健康であり単に作業訓練を休みたい希望が主訴である場合もあります。その見極めをするのが、支援者の役割なのでありますが、精神発達障害をお持ちのスタッフについては、申出を重くとりすぎてしまったり、単に利用者からの体調不良の申出をそのまま上司に伝達するにとどまり、支援者が主体的に考えて対応するのが難しかった事実がありました。
もちろん、一般のスタッフであっても、簡単な作業ではないのですが、通常3か月から6か月程度で概ね職場の考え方に慣れ、主体的に考えた支援をするようになります。精神発達障害のあるスタッフについては、もちろん、一般スタッフ同様に自立していく方もおりますが、多くの場合は、1年から3年の年月ゆっくり時間をかけて考えられるようになっていくのだと思っています。
時間をかけるにあたっては、精神発達障害の方をハローワーク経由で雇い入れた場合は、障害者トライアル雇用助成金、特定求職者雇用開発助成金があり、雇入れから3年間は、月額6万円程度の人件費助成が国から入ることになっています。この人件費助成期間を障害のあるスタッフの育成期間ととらえて、ゆっくり時間をかけた対応をしていくのが、医療福祉の現場において障害者雇用をすすめる大きな考え方であると筆者は考えています。
その上で、医療福祉分野で障害者雇用を進めていく方法論を何点か述べていきます。方向性としては、業務の切り出しと、短時間雇用及び外部関係機関とのつながりが重要になります。
2.短時間雇用から始めてみる

精神障害者の職場定着を進める観点から、精神障害の短時間労働者(週20時間以上30時間未満)を雇用している場合は、雇用率算定にあたり1カウントとする特例措置が継続しています。また、令和6年4月より、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者については、1人雇用した場合、法定雇用率の算定にあたり、0.5人とカウントできるようになっています。障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の雇用機会の拡大を図ろうとする行政の方針にそって、まずは短時間からの雇用を検討するのがよいのではないかと考えます。
医療・福祉業では、福祉行政の基準により、週32時間以上勤務する常勤者を配置し主たるサービスを提供し、かつ、常勤者だけでは福祉行政が求める人員基準をみたさない部分を短時間勤務のスタッフに埋めていただき、シフトを回しているのが一般的です。
精神発達障害者については、週10時間以上から障害者雇用率に算定されるのですから、短時間勤務のシフトを、障害者雇用で満たしていくよう考えていくのが、医療・福祉業界に障害者雇用を受入れていただく近道になります。
3.業務の切り出し
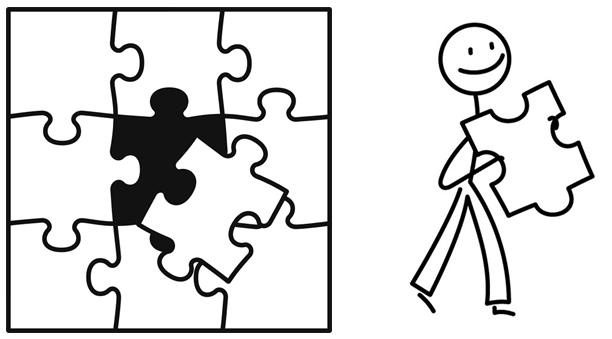
先に書いた通り、サービス業の現場では日々不規則なできごとがあり、対応になれていくには時間をかけていくしかありません。一方で、サービス業の中の医療・福祉業界においては、記録業務や国への報酬請求事務(レセプト)といった全国ほぼ共通、かつ一定量の事務が必ずあります。この定型的な事務に、障害のあるスタッフに関わっていただく余地はあると考えています。例えば、報酬請求の一次入力、記録の抜けのチェックなど業務を切り出すことで一定の事務量は確保できます。また、その事務があることで、他スタッフの業務が軽減されたり、福祉行政から記録漏れを指摘されるリスクが減るのであれば、価値のある仕事と言えます。医療・福祉業界特有の業務を切り出し、障害のあるスタッフに担っていただく可能性を感じています。
4.就労移行支援事業所との連携
医療福祉業界で、短時間スタッフを募集したとしても、人材難で中々応募者がいない現状があります。そんな時には、地域の就労移行支援事業所との連携をお薦めします。
就労移行支援事業所は、障害のある方が2年の年限を決めて就職訓練をする場所です。精神発達障害の方が利用している場合が多く、短時間勤務の希望も多いため、医療・福祉業界とのマッチングが図りやすいと考えています。また、就労移行支援事業所の紹介で入職すると、入職から少なくとも半年は、就労移行支援事業所のスタッフがメンタルや体調管理についての相談援助をしてくれます。雇用した会社は、業務を切り出し、業務の指示に集中し、体調やメンタル面のケアは就労移行支援事業所に任せて役割分担できるのが、障害者雇用を進めやすいと考えています。
本稿では、医療福祉の現場で障害者雇用を進める意義と具体的方法については書きました。職を求める障害者にとっても、人手不足に悩む医療福祉業者にとっても、Win-Winとなる可能性を大いに秘めていると筆者は考えており、今後も推進していきます。
前田福祉社労士事務所
代表 社会保険労務士・介護福祉士 前田 豊/Maeda Yutaka
東京学芸大学卒業後、あきる野市社会福祉協議会に11年間勤務。障がい者施設で支援について学ぶ。平成23年に社会保険労務士として独立し、福祉施設の労務管理を業として行いながら、法定雇用率に関わらず障害者を雇用している中小企業の取材活動を行う。
https://usei116.com/